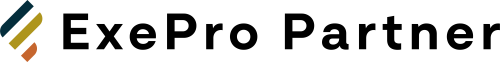その飲食店開業、ちょっと待った!?月100万円が“垂れ流し”になる前に読む話
こんにちは、経営コンサルタントの鍵政達也です。
以前から良くあるご相談が「飲食事業への新規参入」です。他の事業を経営されている方が「海外や地方で面白いお店を見つけたから東京でやりたい」とか、「知り合いのシェフが独立したいって言ってるし、資金だけ出して応援してあげようかな」、「自分の知り合いに使ってもらえば経営が成り立つのではないか?」といった形で、飲食店に参入を検討することが多くあります。
ですが、飲食業は“趣味の延長”や“投資のひとつ”のような感覚で始めるには、リスクが非常に高いビジネスです。
なぜそう言えるのか、できるだけわかりやすくお伝えします。
お店を出して人を雇うと、毎月の固定費が大きくなる
飲食店を持つと、家賃・水道光熱費・人件費などの「固定費」が必ずかかります。たとえば、駅近の立地に10坪ほどのお店を出すと、家賃だけで月30~50万円(東京都心などでは100万円オーバーもざらです)、人件費も正社員やアルバイトを数人雇えば軽く月50万円以上。加えて、仕入れはもちろんのこと、光熱費や消耗品などの経費を考えると、オープンした瞬間から毎月100万円以上の“最低ライン”の支出が発生します。
もちろん、小売店など他の店舗型ビジネスでも固定費はかかりますが、飲食店は特に人手がかかるので“毎日ある程度の集客・売上がないとすぐに赤字になる”という点で難易度が高い業種です。
季節ごと・日ごと・時間ごとの売上の波も大きく、たとえば「雨の日はお客様がほぼゼロ」という日が続くと、それだけで月の利益が吹き飛んでしまうこともあります。
固定費を回収するには、それなりの売上が必要
たとえば、毎月の固定費が100万円かかる場合、利益を出すには一般的には200万円以上の売上が必要です(実際はもっと必要なケースが多いです)。
1人あたりの客単価が1,000円なら、休みなしで営業して1日平均70人以上のお客様に来ていただかないと成立しません。
これを毎日、何年も安定して続けるのは想像以上に大変なことです。
例えば、みなさんが「良く行く」飲食店はどの程度の頻度で行くでしょうか。
仮に2週間に1回とすると、1日70人のお客様に来ていただく必要があるので「よく来てくれる人」だけで集めようとすれば70×14=980人の顧客リストが必要になります。
実際には新規のお客様や、もっと頻度の低い人もいますが、少なくとも1,000人近くの方に「よく来てもらう」必要があるということです。
これはなかなか大変なことです。
売上をつくるには「集客」と「リピート」が必須
安定した売上をつくるには、ただお店を出しただけでは足りません。
先ほどもお伝えした通り、たくさんの人にお店を知ってもらい、来てもらい、そして「また来たい」と思って実際に来てもらわないといけません。
よく「仲間内で使ってもらう店にする」というお話をされる方がいらっしゃいますが、最初のうちは知り合いや家族、取引先などが来てくれても、それだけで売上の大半を支えることはできません(なんせ1,000人集めないといけませんので)。
知り合いだけで月200万円の売上をつくるのは、現実的ではありません。
何らかの工夫で固定費を極限まで下げる(そうすると好立地の場所を借りたり、人を雇うことは難しくなります)か、知り合いではない一般のお客様にも多く利用してもらうことが必須となります。
店舗の“経営”を任せられる人材は、そう簡単には見つからない
「現場のことは任せて、自分は本業に集中したい」と考える方も多いですが、ここに大きな落とし穴があります。
単に料理が上手な人、接客が上手な人と、“店舗の経営を任せられる人”はまったく別物です。
経営を任せるには、
- 売上・原価・人件費の管理ができる
- 客数や口コミを見て原因分析ができる
- トラブルや人間関係に対応できる
- スタッフの採用・育成を行える
- SNSや販促も含めて戦略を立てられる
こうしたことを総合的に担える人が必要です。
しかし、現場でこうした能力をすべて持ち合わせている人は多くなく、いても採用が難しいのが実情です。
こういった能力を持っている方はご自身で独立される場合も多いです。
そのため「信頼して任せていたのに、気づけば赤字続きだった」というケースは実際に多く見られます。
趣味や“片手間”の運営では、なかなかうまくいかない
飲食店の成功には、立地・メニュー・価格・接客・SNSでの情報発信・広告・コストコントロールなど、地道で細かい施策が欠かせません。
少しでも業績が奮わないと感じたら、すぐに原因を探り、対策を打つようなスピード感が必要です。
つまり、月に数回だけ様子を見に行く“オーナー業”では、お店の現場感覚をつかむのが難しく、結果的に失敗する可能性が高くなります。
もちろん飲食業でオーナー業をされている方はいらっしゃいますが、多くはご自身が飲食店での経験があり創業当初は現場に立たれていたような方が多いです。
だから町中華は最強のビジネスモデル
ここまで読んで「飲食店はそんなに難しいの?」と思われた方もいるかもしれません。
でも、街を見渡せば、何十年も続いている飲食店があり、その代表格がいわゆる「町中華」です。
ご夫婦で経営されているような街角にある昔ながらの中華料理屋さんです。
なぜ、町中華のようなお店が生き残っていけるのか?そこには、飲食店経営の本質ともいえるヒントが詰まっています。
固定費が極めて低い
多くの町中華は、自宅の1階をお店にしていたり、長年借り続けている物件で家賃が極端に安かったりします。
また人を雇っていない(雇っていてもピーク時のアルバイトなど)ことにより、高額な固定費に圧迫されることがなく、低い損益分岐点で経営が成り立つのです。
オーナーが現場に立つので、顧客の声や現場の機微がわかる
来店したお客様の反応、混雑する曜日や時間帯、スタッフの様子や食材の状況などを肌で感じながら即座に改善できるのは、経営者自身が現場にいるからこそです。
これは、他人に任せる“投資型オーナー”には絶対に真似できない強みです。
オーナーが現場に立つので、コストコントロールもしやすい
仕入れをどう調整するか、人をどれだけ入れるか、どこで手間をかけてどこで手を抜くか。
こうした判断も日々の現場を知っている人だからこそ可能になります。
現場を知っている=無駄が見える、ゆえに大きくない売上でも利益が残せます。
常連客がつきやすく、客数が安定する
地域密着で家族経営、気軽に利用できる価格帯で、近隣の方が日常的に通ってくれます。
SNSでバズらなくても、地元に根差した商売で安定的なリピート売上が見込めます。
町中華のすごさ
町中華は「コストを極力かけず、自分で見て・感じて・調整しながら、地元のお客様にしっかり価値を届けてリピートしてもらう」という、飲食業において極めて合理的なスタイルとなっています。
もちろん、全ての飲食店が町中華のように家族経営できるわけではありませんし、まったく同じことを真似するのは現実的ではありません。
でも、もし飲食店を始めたいなら、この町中華的な考え方 「現場に立つ」「無駄を減らす」「お客様と向き合う」という本質的な部分にこそ、一店舗目の成功のヒントがあると言えるでしょう。
飲食業は「甘くない」が、きちんと向き合えば面白い
他の事業でうまくいっている人ほど、飲食業を気軽に考えがちですが、飲食業はまったく別の世界です。
むしろ、競合が多く、労働集約的で、流行り廃りも激しい難易度の高い事業です。他業種の感覚で参入してしまうと、想定外の赤字やトラブルに見舞われる可能性が高いです。
一方で、時代やニーズに合った長く愛されるお店をつくることが出来たら、お客様の喜びや現場の熱量が近くで感じられるとてもやりがいがある事業であることも確かです。
だからこそ、もし飲食店を始めるなら「趣味の延長」や「いっちょ噛み」ではなく、もうひとつ本業を持つくらいの覚悟と時間とエネルギーを注げるかどうかが問われます。
みなさんがもし本気で「飲食業で人を喜ばせたい」「長く続く愛されるお店を作りたい」と考えるのであれば、ぜひその想いをカタチにしてほしいと思います。
ただし、“気軽な気持ち”ではなく、“経営者としての本気”で臨むことをおすすめします。
投稿者プロフィール
最新の投稿
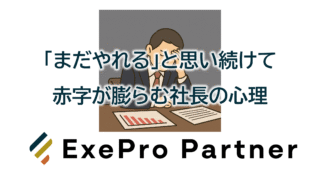 ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理
ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理 ブログ2025年9月3日「経営目線で考えろ」は危険ワード?任せ方を間違える社長の共通点
ブログ2025年9月3日「経営目線で考えろ」は危険ワード?任せ方を間違える社長の共通点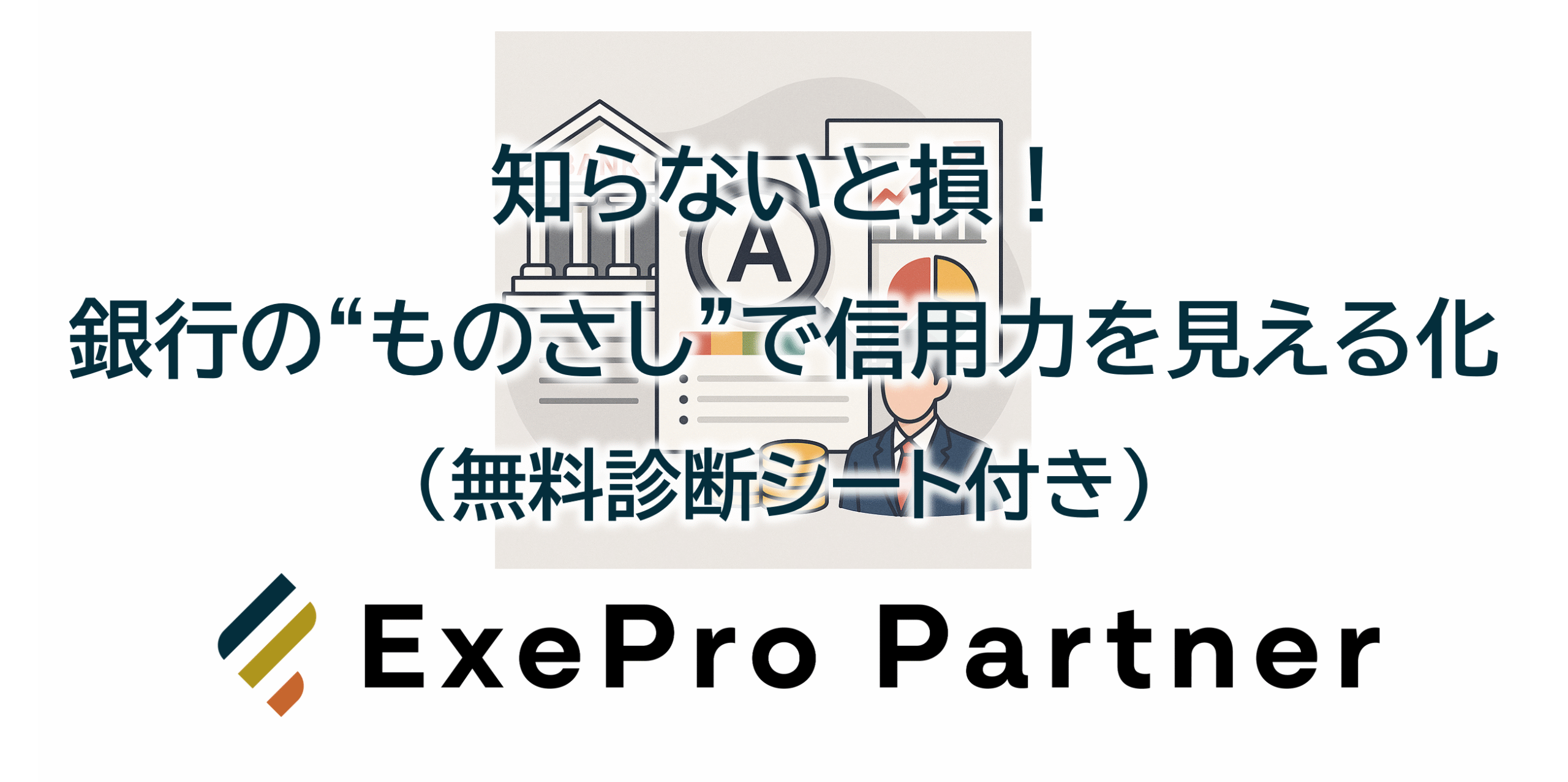 ブログ2025年6月9日知らないと損!銀行の“ものさし”で信用力を見える化(無料診断シート付き)
ブログ2025年6月9日知らないと損!銀行の“ものさし”で信用力を見える化(無料診断シート付き) ブログ2025年6月4日そのKPI「手段が目的化」していませんか?── イラっとした営業から見るKPI設計の難しさ
ブログ2025年6月4日そのKPI「手段が目的化」していませんか?── イラっとした営業から見るKPI設計の難しさ