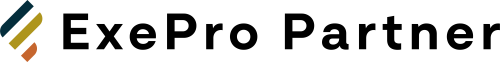そのKPI「手段が目的化」していませんか?── イラっとした営業から見るKPI設計の難しさ
こんにちは、経営コンサルタントの鍵政達也です。
今日は少しイラっとしてしまった営業とそこから考えるKPI設計というテーマでお話していきます。
開封率だけが目的?不快なDMに感じた違和感
ある日、ふと目に留まったダイレクトメールの件名に、思わず眉をひそめました。
「●●していないあなた、それじゃ成果なんて出ませんよ」
──とでも言いたげな、かなり煽った文面。
同業他社(しかも大手)のその“突き放した上から目線”がどうにも引っかかって、気分がよくありませんでした。
後日、たまたまその会社のことを知る知人と話す機会があり、このDMの件を話題にすると、
「ああ、あそこはたしか“開封率”がKPIなんですよ。開封されさえすれば良し、みたいな運用になってるかもですね」
という言葉が返ってきました。
なるほど、数字を追うなら「開かせる」ことが優先されます。
とはいえ、そのために相手を不快にさせるような伝え方をしてしまっていいのだろうか…
違和感の正体が少し見えた気がしました。
信頼していたメディアの“残念な営業電話”
もう一つ、印象に残った出来事があります。
あるメディアが主催するオンラインセミナーに参加したときのこと。
そのメディアは普段から質の高い記事を発信しており、個人的にも好感を持っていたので、セミナーにも自然と期待していました。
セミナーは内容も非常に充実していて、受講後の満足感も大きかったのですが、数日後、突然営業電話がかかってきました。
(営業電話はいつも突然ですが)
驚いたのは、その話し方と姿勢です。
「今、お時間よろしいですか?」といった一言もなく、
開口一番、一方的に話しはじめました。
こちらが急ぎの対応で忙しい時間だったこともあり、
営業なら今すぐは興味がない、いまは忙しいので必要なことならメールして欲しい旨を伝えましたが
それでもなお、話を切り上げようとせず、電話での説明とアポイントの取得を続けようとされたのです。
“どうにかアポイントを取りたい”という気持ちは伝わってきましたが、
その熱意が、相手の状況への配慮を押しのけてしまっていたように思います。
誤解のないように言えば、私は電話での営業行為そのものを否定したいわけではありません。
しかしこの一件で、ふと頭をよぎったのは、
「これは“アポ獲得件数”がKPIになっているのでは?」
という疑念でした。
目標達成のプレッシャーが、
本来その会社が大切にしていたはずの“丁寧な情報発信”の姿勢と食い違ってしまっている。
そんな残念さを感じたのです。
KPIの強みと弱さ──なぜ「手段の目的化」が起きるのか
もちろん、KPI自体を否定するつもりはありません。
むしろ、物事を見える化し、改善のきっかけをつくるという点では、
KPIは非常に有効な手法であることは間違いありません。
ですがその一方で、今回のような体験からあらためて感じたのは、
KPIをそのまま“評価”に使ってしまうことの危うさです。
本来は「目標に近づくための指標」であるはずのKPIが、
いつの間にか「評価されるための目標」にすり替わってしまう。
そうなると、現場ではどうしても“数字のための行動”が先行してしまいます。
「開封されるために刺激的なタイトルにすればいい」
「とにかくアポを取ることが正義」
──そんな風に本来の目的が置き去りにされていく。
これが、“手段の目的化”という状態なのだとあらためて実感しました。
KPIを設計する際に、大切にしたい3つの視点
では、どうすればこうした本末転倒を防ぐことができるのでしょうか。
私なりに意識しているのは、以下の3点です。
1. 目的とつながっているか?
そのKPIは、何のために追っているのか。
開封率やアポ件数は、あくまでも目標達成のための通過点にすぎないはずです。
2. 行動の“質”を下げていないか?
数字を追うあまり、相手への配慮やブランドの信頼性を損なっていないか。
「やりすぎていないか?」をチェックする視点は欠かせません。
3. 評価ではなく、改善の道具になっているか?
KPIは“成績表”ではなく、“議論の材料”として活用することが大切です。
数字が伸びなければ叱責するのではなく、「なぜ伸びないのか」を一緒に考える。
そのための指標がKPIのあるべき姿でしょう。
そんな姿勢が、健全なチームをつくる土台になると思います。
おわりに|その数字の先に、何を見ているか
KPIは、行動を促し、成果を見える化するための優れた道具です。
ただし、それはあくまで“目的に近づくための目印”であって、目的そのものではありません。
一つのKPIだけを重視しすぎることで、
かえって本来大切にすべき成果や信頼を損なってしまう。
そのようなケースは、現場でも少なくないように思います。
もちろん、短期的に誤った方向に進んでしまったとしても、
その先にある別のKPI(今回の例でいえば成約率など)が下がることで、
結果的に「アポイントのアプローチがおかしかった」などと気付けることもあります。
しかし本来は、そういったことにならない状態を作っておくのが理想です。
そのためには、KPIの数字にばかり目を奪われるのではなく、
「なぜその指標を追っているのか」
「何を実現したくて、その行動をしているのか」
という目的意識を、チーム内で共有することが欠かせません。
目的が明確に共有されていれば、
仮にKPIにズレが生じたとしても、早い段階で立ち返ることができますし、
現場での判断にも“芯”が通るようになります。
KPIは便利な道具です。
でも、道具を活かすのは、あくまでそれを使う人の“意図”や“姿勢”です。
数字にとらわれるのではなく、
その向こう側にある「信頼される行動とは何か」を考えること。
それが、KPIをただの“ノルマ”にせず、前向きな対話や成長につなげる鍵なのだと思います。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました
お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました
お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました
お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました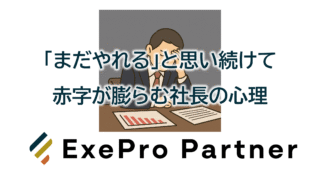 ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理
ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理