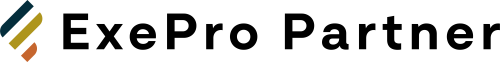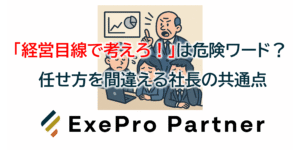「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理
こんにちは、経営コンサルタントの鍵政達也です。
今回は赤字事業の撤退というテーマです。
経営において「損切り」は売上を伸ばすことと同じくらい、いやそれ以上に大事なものです。
しかしながら、そう簡単に踏ん切りがつかないという場面も実際には多くあります。
「まだやれることはある」
「ここでやめたら失敗を認めることになる」
「社員や取引先に迷惑はかけられない」
気持ちは痛いほどわかります。
けれども、その「もう少し」が積み重なるうちに、赤字は膨らみ、会社全体を圧迫してしまうのです。
撤退の決断を遅らせる社長の心理と、冷静に判断するための視点について整理していきます。
事例:飲食店の新規出店での迷い
ある飲食チェーンが新しく店舗を出しました。
オープン直後は話題性もあり、最初の数か月は売上好調。
しかし徐々に客足が遠のき、赤字店舗に転落します。
役員会では「立地の問題では」「客層が違ったのでは」と議論が交わされましたが、結論は出ません。
一方で、「オープン時の勢いを取り戻せるはずだ」「まだやれることがある」という声も強く、社長は撤退を決断できませんでした。
結果として赤字は膨らみ、他店舗の利益まで食い潰すことに。
もし早めに見切りをつけていれば、会社全体の体力は守れたはずです。
sunk cost──「ここまでやったのに」の罠
飲食店の事例でも見られたのが、いわゆる「sunk cost(埋没費用)」の心理です。
内装工事や広告宣伝、採用教育……すでに多額のコストを投じたからこそ、「ここでやめたら全部無駄になる」という感情が強く働きます。
社長の心の声は
「あれだけ改装に投資した」
「スタッフを採用して教育もした」
「ここでやめたら全部ゼロになる」 ・・・
けれども冷静に考えれば、過去に使ったお金や時間はすでに戻ってきません。
未来を考える上では「これから先に投じる経営資源を回収できるかどうか」こそが判断基準になるべきなのです。
社員・取引先への責任感が判断を鈍らせる
「この店舗を閉じたらスタッフはどうなるのか」
「取引先にも迷惑をかけてしまう」
責任感の強い社長ほど、この思いに縛られます。
現場の雰囲気も「ここで頑張らないと他のスタッフに申し訳ない」という空気になりやすい。
しかし、続ければ続けるほど資金繰りは悪化し、むしろより多くの社員や取引先を巻き込むリスクが高まります。
撤退を先延ばしにした結果、「結局は全体の雇用や取引を守れなかった」というケースが多く見られます。
撤退は「誰かを切り捨てる決断」ではなく、「全体を守るための決断」
この視点を持てるかどうかで、会社の未来は大きく変わります。
プライドと世間体──「失敗を認めたくない」
例えば、飲食店の出店は社長の肝いりで始まったプロジェクトだった、という場合
「撤退=自分の判断ミスを認めること」になり、プライドが決断を邪魔します。
「失敗した社長だと思われたくない」
「今さら撤退したら社員に顔向けできない」
社長の立場を考えれば、この気持ちは痛いほど理解できます。
ただ、実際には「早めに撤退できた社長は冷静で優秀」と評価されることも少なくありません。
逆に「引き際を誤った社長」は、その後の経営判断すべてに対して信頼を失うことすらあります。
「現場の声」に引きずられる危うさ
現場からは「メニューを変えればまた集客できる」「SNSキャンペーンで集客できる」といった意見も出ました。
現場の声は前向きで力強い反面、希望的観測が混ざりやすいものです。
こうした声に社長自身の期待が重なると、判断はますます遅れてしまいます。
そこで有効なのが、シミュレーションで現実を可視化すること。
たとえば毎月100万円の赤字が出ている店舗で、粗利率が変わらないと仮定すると、黒字にするには客数を倍増させる必要があるかもしれません。
「倍の客を呼べるのか?」と冷静に問い直せば、「小手先の改善では難しい」という現実が浮かび上がります。
1年続けた場合の損失を「見える化」する
さらに、撤退を遅らせることの重さを実感するには「1年続けた場合にどれくらいの損失になるか」を数値化するのが効果的です。
- 毎月100万円の赤字 → 1年間で1,200万円の損失
- 毎月200万円の赤字 → 1年間で2,400万円の損失
これだけの赤字だと会社全体の利益を食いつぶし、資金繰りが行き詰まる可能性も大いにあり得ます。
損失が膨らめば膨らむほど、金融機関などからの信頼も低下します。
「撤退できない会社」というレッテルは、今後の資金調達や新規取引にも影響しかねません。
また、このお金があれば新しい店舗の出店資金や、既存事業の成長投資に充てられるはずです。
つまり撤退を先延ばしするというのは、「未来のチャンスを失っている」ということでもあるのです。
判断を早めるための3つの工夫
- 撤退基準を事前に決める
「赤字が3期続いたら撤退」「客数が○%以下に落ちたら撤退」など、明確なルールを持つ。 - 外部の視点を取り入れる
顧問税理士、コンサルなど、第三者の冷静な意見を定期的に取り入れる。 - 撤退後のシナリオを描いておく
「スタッフは他店舗に異動」「厨房設備は別店舗で再利用」といった道筋を準備しておくと、心理的ハードルが下がる。
まとめ──撤退は「次に進むための判断」
飲食店の新規出店の事例ように、社長の心理には、
- sunk cost(投資を無駄にしたくない気持ち)
- 社員や取引先への責任感
- プライドと世間体
- 現場の声
が絡み合い、撤退の決断を遅らせます。
けれども撤退は「終わり」ではなく、「次に進むための判断」です。
冷静にシミュレーションをすれば、「小手先の改善では難しい」「続ければ損失が膨らむ」という現実が見えてきます。
感情ではなく、数字とシナリオで判断する。
それが、経営者にとっての冷静で勇気ある一手になるのです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
 お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました
お知らせ2026年1月1日月刊 近代中小企業 に寄稿しました お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました
お知らせ2025年12月10日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました
お知らせ2025年11月13日国内最大級の管理部門と士業の専門サイト「マネジー」に寄稿しました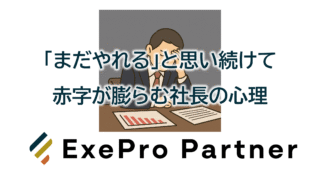 ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理
ブログ2025年10月4日「まだやれる」と思い続けて赤字が膨らむ社長の心理